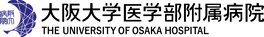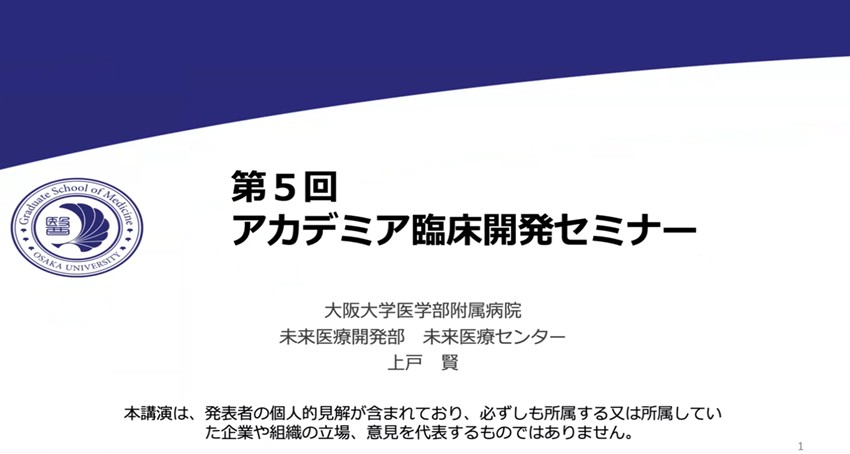(セミナーレポート)第5回 アカデミア臨床開発セミナー
PMDAでの経験から語る:医療機器承認審査の舞台裏
2025年3月7日、令和6年度の第5回アカデミア臨床開発セミナーをオンラインで開催しました。
今回のセミナーでは、大阪大学医学部附属病院未来医療開発部 未来医療センター 上戸 賢先生お迎えし、「PMDAでの経験から語る:医療機器承認審査の舞台裏」と題してご講演いただきました。
まず、医薬品医療機器等法の目的と規制について説明がありました。PMDAは保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行い、これにより保健衛生上の向上を図ることが大きな目的である、とお話されました。さらに承認審査においては提出された資料をもとに、臨床上もたらされる有効性のベネフィットと臨床現場に導入された際に発生しうるリスクを天秤にかけ、リスクがベネフィットと比較して許容されるようであれば承認審査のプロセスが進んでいくとのことでした。
PMDAと厚生労働省の役割については、主にPMDAが医薬品等の審査・調査・治験相談など、科学的な判断の実施を行い、厚生労働省が制度設計や法律改正など、行政措置等の実施を担当している、と比較されました。
次に医療機器のクラス分類についてのお話では、リスクに応じてクラスI(一般医療機器)、クラスII(管理医療機器)、クラスIII・IV(高度管理医療機器)に分類されること、そして各クラスの製造販売における手続きの違いについても述べられました。また、プログラム医療機器(SaMD)については、同じ機能でも標榜により該当性が変わるため、どのような標榜をしたいか検討し、製品の位置づけを整理することが重要であると説明されました。
最後に医療機器の薬事開発における要求事項の中で「臨床的位置づけ」「概念的要求事項」の解釈についてもご説明いただきました。「臨床的位置づけ」については、この製品により解決したい臨床現場の課題は何なのかを整理することが製品の評価を考える際に重要であり、既存の治療法/診断法との比較をすることから始めると整理しやすいとのことでした。「概念的要求事項」については洗濯機を例に、最低限満たさないといけない項目と市場ニーズや開発コンセプトの要素をすべて、または組み合わせた「製品が有すべき性能を概念的に示したもの」として評価ポイントを教えていただきました。
今回のセミナーでは、医療機審査について包括的にわかりやすくご説明いただき、実用化に向けたプロセスについての理解が深まりました。